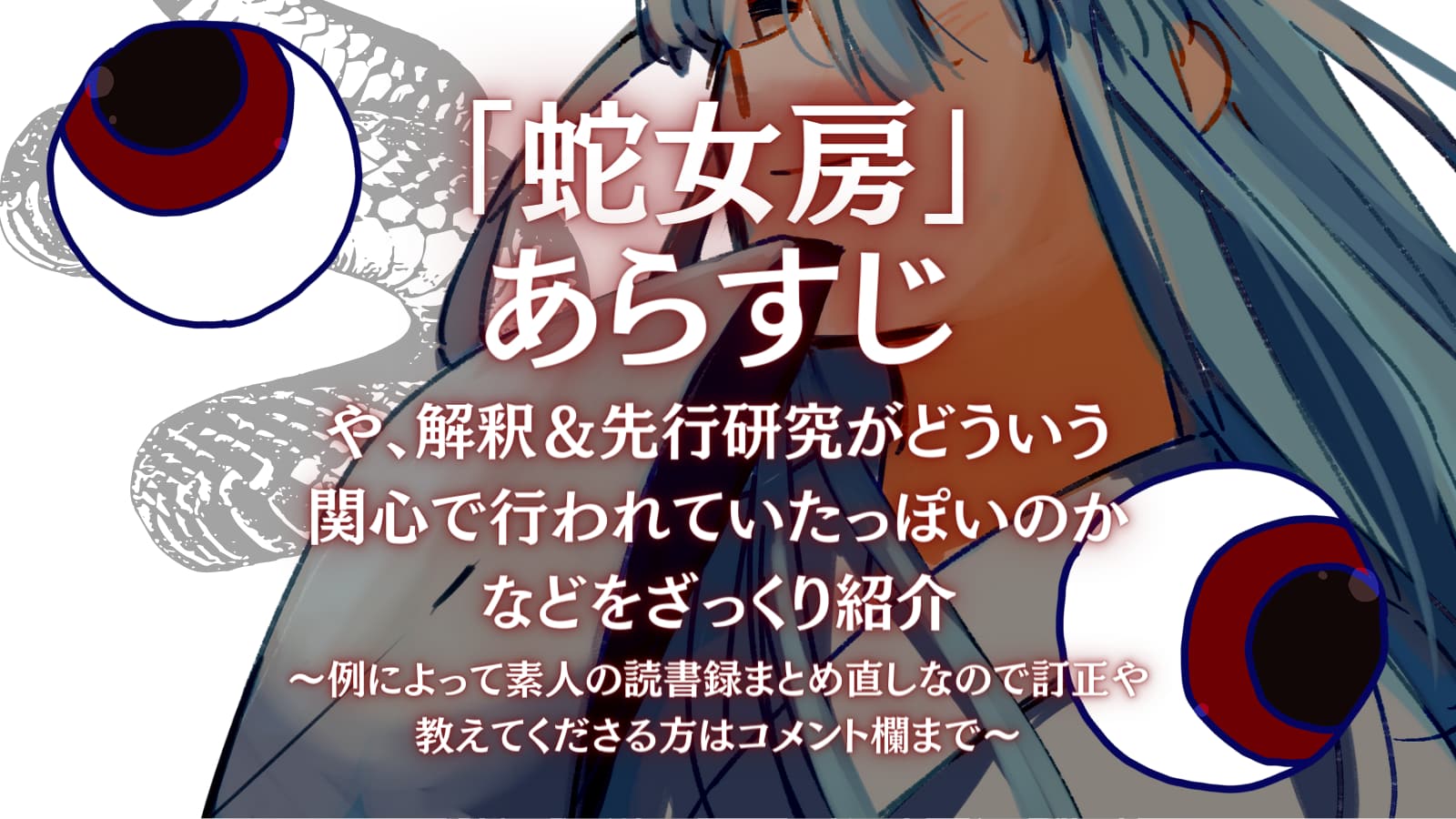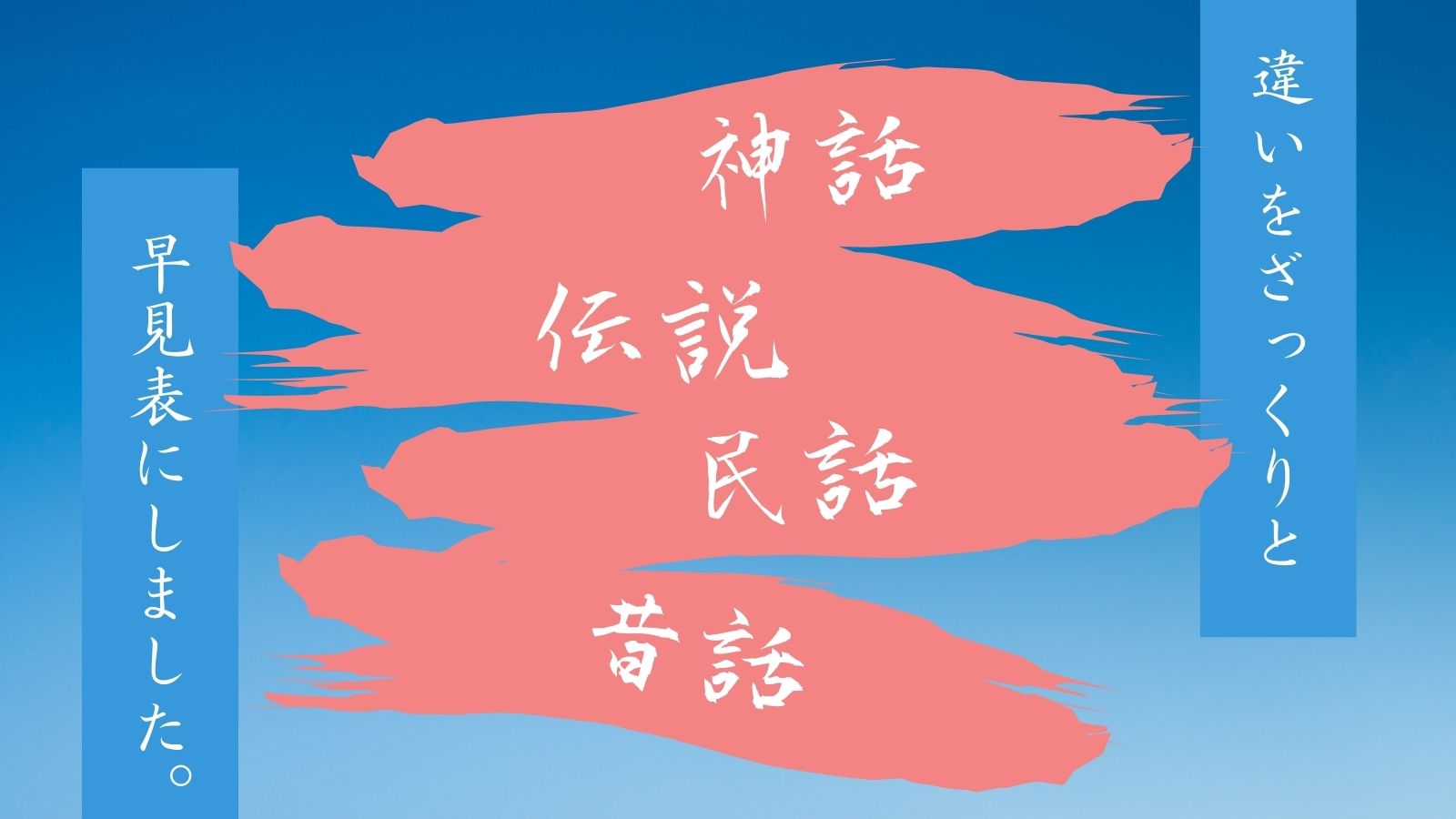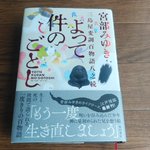このコラムでは、いわゆる「蛇女房」という名前で有名な、蛇の異類女房(動物嫁)譚の『あらすじ』や沿革についてざっくりと解説していきます。
といっても筆者は過去も現在も研究者であったことは一度もない完全なる一般人であり、趣味の延長としてこのコラムを記しています。読んだ書籍や論文を、自分の思考の整理も兼ねて検索需要に合わせてシンプルにまとめなおす、というのがこのコラムの方針です。
ですので、ここで書かれている内容が現在の研究とは乖離していたり、解釈を誤っていたりする可能性は充分ございます。孫引きもバンバン行っています(原典にさかのぼれる機会があれば随時更新、という感じです)。ご了承のうえお読みください。

コメント欄は解放してありますので、お心が向いた方は、訂正やさらなる参考書など教えてくだされば幸いです。
「蛇女房(蛇の目玉、三井寺の鐘)」伝承のあらすじ
▽トークノベル形式で読みたい方はこちらへ
▽構造で見る「異類女房譚」
植月惠一郎「ラヴクラフトの〈反転〉する恐怖」(「西洋文学にみる異類婚姻譚」収録)による、『異類婚姻譚の最大公約数』に、以下のようなものがあります。
邂逅-人間が動物を危難から救済する
返礼-その動物が人間に化けて助けてくれた人のものを訪れる
共生-生活を共にし、その際、守るべき契約や規則(禁忌)を確認する。
繁栄-禁忌を遵守し、そういう生活を営むことで、富が生まれる。
破局-タブーを犯し、動物の正体を知ってしまう
別離-動物は人間のもとを去る
(小鳥遊書房,2020年「西洋文学にみる異類婚姻譚」p.191)
これは「異類女房譚」における最大公約数ではないか?と思いますが、このコラムで取り扱うのは「蛇女房譚」であり、日本昔話における蛇女房譚もまたこの構造を持っていると思うので、紹介いたします。
▽あらすじ
子どもたちにいじめられている蛇を、通りかかった若者が助ける。その晩、若い女が男の家を訪ねてきて宿泊を願う。そのまま居ついて、二人は夫婦になる。
あるいは…
三井寺に百度参りしている女性に惚れた男が、女性に結婚を申し込む。女は百度参りが終わったら結婚を受け入れるという。そうしてやがて男と女は夫婦になる。
※他にもさまざまなパターンがあります。
女は妊娠して子どもを産むことになるが、「お産しているところを決して覗いてはならない」と言う。しかし男は覗き見てしまう。そこには、人間の赤子を抱いた蛇の姿があった。
姿を見られたことを知った女(蛇)は、片方の目玉を赤ん坊に与えて去る(「この目玉があれば、乳がなくても赤子は育つ」と言う)。※このとき「もし何かあれば〇〇へ来てください」と自分の居場所を言い遺して去る場合もある
目玉がだんだん小さくなり、なくなる
あるいは
目玉の噂を聞いた殿様に取り上げられる
男は、母である蛇に会いに山奥の池へ行く。池で呼びかけると女(蛇)が出て来て、もうひとつの目玉を取り出して渡す。それから「これで両目が見えなくなり、子どもの成長も見えなくなった」「子どもを寺の鐘つきにして、朝晩の鐘を鳴らしてほしい」と男に頼む。そうして子どもはその玉で無事に成長し、寺の鐘つきになったという。
おしまい。
蛇を助けた若者の漁師のもとにきれいな娘が来て、女房となる。女房が赤ん坊を産む時、見るな言われるが男は見てしまい、蛇であることを知る。女房は去るが、男に玉を渡し、子どもになめさせるように頼む。子どもはよく泣くが玉になめさせると不思議に泣きやむ。しかし、このことが殿様に知れ、取り上げられる。すると女房がもう一つ玉を渡し、これで両眼をあげたので目が見えなくなってしまった、朝晩がわかるように三井寺の鐘をついてほしいと頼む。
(引用:『志度寺の「当願暮当之縁起」について』より 長谷川 隆による要約
三井寺の下で、子どもが一匹の小蛇をいじめていたので、男がこの蛇を助けてやる。美女が来て泊まり、夫婦になる。やがて子どもが生まれる。出産の様子を見てはならないと言われたにもかかわらずのぞくと、大蛇がいる。かつて助けた小蛇であった。正体が知れたので、目玉を渡して去る。その玉を役人に取られる。三井寺の下に行くと、女があらわれて、もう一つの目玉を渡し、両目を渡したので盲目になってしまったから、朝晩がわかるように鐘をついてくれと言って消える。(香川県高松市附近)
(引用:角川ソフィア文庫「鬼と日本人」p.254 小松和彦による要約)
このお話は「三井寺」に関わる『伝説』として分布しているらしい…
昔話(≒民話)というのは、
往々にして「時代はいつでも」「場所はどこでも」
という特徴のものを指すのですが、
このお話についてはどうも
「三井寺の鐘に関連したお話として全国に分布している」
という特徴があるそうです。
日本の社会学者、民俗学者の鳥越皓之氏は、この説話について
①「蛇女房・目の玉型」の昔話は地域にへだたりなく全国に分布している
(鳥越皓之「蛇女房・目の玉型考察ー琵琶湖総合開発問題とかかわらせて―」1984年)
②琵琶湖、三井寺という固有名詞をそなえた昔話も、九州地域を除いて、全国にかなり広く分布している。
…として、このお話が
「昔話」というより「伝説」的であることを述べています。
▽「昔話」と伝説の違い
これもまた学術的な立場(?)によって微妙に違うようですが、認識しているのですが、ざっくり説明すると次の理解でとりあえずはよいのではないかな…と思います。
昔話→フィクション物語
伝説→実在の人物や土地にまつわる物語
もう少し詳細をまとめているので、気になる方は↓のコラムを御覧ください。
「目玉」は何の象徴なのか?-日本神話における「潮満珠・潮干珠」の伝説から?
そうして、鳥越皓之氏は、「本質的にはこれ(目玉)は何かの暗喩であろう」として、この昔話(伝説)の源流を日本神話にまで辿り、「潮満珠・潮干珠」あたりから来ているのではないか…としています。
鳥越氏はこれを「ヤカン説(※マユツバ物のお話)」だと謙遜しておられますが、小松和彦氏も似た意見に落ち着いているご様子。
「蛇女房」の昔話は“子ども”よりも“目の玉”の要素の方を強調しているかにみえる。しかも、多くは三井寺の鐘と結びつけた伝説的色彩の強い話が多い。おそらく、これには三井寺に集まった盲僧(琵琶法師)との関係や、大蛇(竜神)がもつという「潮満玉」と「潮干玉」や仏教化された「如意宝珠」との関係が反映されているためであろう。
平成30年,小松和彦「鬼と日本人」p.256,株式会社KADOKAWA
▽「シオミツ珠・シオヒル珠」とは
『古事記』などに登場する日本神話の神。弟の山幸彦(ホオリノミコト)は,兄の海幸彦(ホデリノミコト)から借かりた釣り針を漁でなくして海にさがしにいく。そして,海神から釣り針のほか,シオミツ玉・シオヒル玉をさずかり,この2つを使って意地悪な兄をこらしめた。◇これと類似の話は世界各地かくちに分布する。
キッズネットうみさちやまさち【海幸山幸】
他の異類女房譚との違い
扱われ方―嫌悪されてもおらず過剰に畏怖されてもおらず、蛇と狐は並んで「両義的」…カモ

…という塩梅で、古川のり子氏の整理によると、他の代表的な異類女房譚と詳細にくらべてみると
「狐と蛇女房の扱いは、他の異類嫁よりも両義的(※)な印象」
と言えそうです。
小松和彦氏は、「狐女房」譚は「蛇女房」のバリエーションだと考えているようです。(平成30年,小松和彦「鬼と日本人」p.256)
(※)二つの対立する立場や意見のどちらの意味もとることができるさま、または曖昧なさまを意味する表現。
▽「その他の異類女房譚」の種類をざっくり知りたい方は
お話の構造で見る他の異類女房譚との違い
日本の昔話のほかの異類女房譚との違い
| 「大成」(※)分類 | 女性のプロポーズ | 女性の禁止 | 女性の本性発覚 | 離婚 | 子ども |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 蛇女房 | 〇 | お産を見るな | 〇(のぞき見) | 〇 | 1人(目玉を子どもの為に残す) |
| 111 蛙女房 | 〇 | × | 〇(親元に帰る際に尾行) | 〇 | 無 |
| 112 蛤女房 | 〇 | × | 〇(のぞき見) | 〇 | 無 |
| 113A魚女房 | × | 水浴び姿を見るな | 〇(のぞき見) | 〇 | 3人のうち2人を残す (男が後妻をもらい、子どもは往き失せする) |
| 113B魚女房 | 〇 | × | 〇(のぞき見) | 〇 | 無 |
| 115鶴女房 | 〇 | × | 〇(親元を問いただす) | 〇 | 無 |
| 116A狐女房 (聴耳型) | 〇 | お産を見るな (男は禁を守る) | 〇(女が自ら語る) | 〇 | 1人(偉大な人となる) |
| 116B狐女房 (一人女房型) | 〇 | × | 〇(子どもが見つける) | 〇 | 1人(長者になる) |
| 116C狐女房 (二人女房型) | 〇 | × | 〇(尾を出して見られる) | 〇 | 1人(泣かぬ子になる) |
(※)「大成」…「日本昔話大成」の略。関敬吾による日本の昔話集収録
この表から分析すると、「日本の蛇女房」のお話はほかの異類女房譚の違いは
・「見るな」は『お産』
・残すのは「目玉」…(蛤女房や魚女房は「体内から出た排泄物」/鶴女房は「体を覆う体毛」、蛇女房は「器官」)
といった特徴がありそうです。
これらについての解釈云々…となってくると、
話がややこしくなっていきそうです。
これらへの言及をもし見つけたら追記します。
「蛇婿(蛇聟)」と「蛇女房」のわかりやすい違い
蛇聟→蛇は殺害されるパターンが主流(故意にせよ、結果にせよ)
蛇女房→離別にはなるけど、殺害ではない
(…追って詳細記述…)
▽「蛇婿(蛇聟)」と「蛇女房」の詳細コラム
他国の異類女房譚(動物女房譚)とのわかりやすい違い
日本のドイツ文学者、昔話研究者の小澤俊夫氏は、「正体が露見して去る」にあたってこの『去る理由』がお話によって違うところが気になっていたようで、次のように整理されています。曰く
Ⅰ動物が人間の女性の姿で妻にくるが、正体を見られ、子を置いて去る
Ⅱ動物が人間の女性の姿で妻にくるが、正体を指摘されて怒って去る
Ⅲ動物が人間の女性の姿をしているとき、むりに妻にされる
(参考…小澤俊夫「世界の民話」p.116/1979年/中央公論社)
…ということで、以下、ぞれぞれのパターンに当てはまる民話をちょっとだけ紹介していきます。
Ⅰ動物が人間の女性の姿で妻にくるが、正体を見られ、子を置いて去る
- 蛇女房(日本)
- 蛙女房(日本)
- つる女房(日本)
- 狐女房(日本)
- はまぐり女房(日本)
- 龍女(韓国)
- ニクセ(妖精)と人間の結婚(ゲルマン民族) など…
(参考…小澤俊夫「世界の民話」pp.117-133/1979年/中央公論社)
このパターンは日本の多くの異類女房譚を含んでいるので、これが日本の異類女房譚においては主流と考えてよいハズです。
山から薪を切っては町で売って暮らす若者がいた。ある日、町からの帰り道に山を通りかかったさい、子どもたちが鶴の足に縄をかけて遊んでいたのを見た若者は、自分の売り上げた金でその鶴を買い取って逃がしてやる。
その晩、若者の家に美しい娘がやって来て「一晩泊めてくれ」と頼んでくる。翌朝、娘は両手をついて「嫁にしてくれ」と言ってくる。
嫁として迎えることを承諾すると、娘は「ひとつ布を織るから、出来上がるまで覗かないでほしい。7晩目にはきっとお気に入りの布を作り上げてみせる。」と言って部屋に閉じこもる。7日目の晩に一反の布を若者に渡して、売るように言う
布は、思っていた倍の値段で売れ、次はその1.5倍で買い取ってくれるという話になったため、帰宅した若者は妻にまた布を織るように要求する。そうして妻はまた部屋に閉じこもるが、そのような質の高い布をどうして織れるのか心配になった若者は、部屋を覗いてしまう。
すると、丸裸に近い姿になった鶴が、自分の体から一本一本毛を抜いて布を織っているのが見えた。
驚いた若者は、声を出してしまう。その晩遅くに機織りの音が止むと、妻が布を持って出て来て、若者に自分の正体が先日助けられた鶴であることを告げる。それから、「正体を見られたからには帰らなくてはならない」と言って、飛び去って行く。
鶴が二回回ったところを鶴巻田といい、糸をとった川を機織り川という。金蔵(若者の名)が出家して寺を建てたのが珍蔵寺で、その寺には鶴の織った曼荼羅が残っているという。
小澤俊夫「世界の民話」からの要約。
事例17 高麗の太祖の祖父の妻は龍女であった。彼女は大井という井戸を掘って,西海の竜宮に通ったという。この龍女は常に夫に向かって「私が竜宮に戻るときには決して私の姿を見てはいけない。もしこの約束を破ったら私は永遠に帰ってこない」と言っていた。ある日,夫がこっそり彼女の行動をのぞくと,彼女は侍女とともに黄色い龍になって井戸に入り,そこから五色の雲があらわれた。夫はびっくりしたが黙っていた。龍女は帰ってくると,「あなたが約束を破ったので,私はここにいられなくなった」と大変怒った声で夫に言い,侍女といっしょに龍になって井戸に飛び込んだまま,帰ってこなかった。 一京畿道開城府一(崔編著1977:16-17)
異類婚姻謂の類型分析日韓比較の視点から 川 森 博 司 より引用
※小澤先生も断っていらっしゃいますが、この分布はあくまでこの書籍の時点の整理となります。研究が進んでいるかもしれませんので、ご存知の方でお心が向く方がいらっしゃいましたら参考文献などをコメント欄で教えてくださいますと幸いです。
Ⅱ動物が人間の女性の姿で妻にくるが、正体を指摘されて怒って去る
- 虎女房(中国) など…
(参考…小澤俊夫「世界の民話」p.133/1979年/中央公論社)
兄弟で所有している瓜畑の夜番をさせられている弟がいた。弟は不公平に思い、十日ごとの交代制にするように兄と掛け合い、まず弟が十日目に番に出る。4晩目、遠くから虎のようなものが駆けてくるのが見えたので、弟は小屋に入る。まもなく戸を叩く音と人間の声がしたので開けると、そこには美しい女がいたので家の中に入れた。弟は「近隣の家の娘」だと思い、夫婦になる。
女は毎晩やってきて、戸の外で虎の皮を脱いで、美女に姿を変えて男の元を訪問しては談笑する。ときには鹿肉などを持参した。そうして翌朝早くに、床を離れて戸の外で皮を被り、また虎になって去っていく。男はそれに気づかなかった。
ひと月たっても戻らなかった弟を不審に思った兄は、ある日小屋を覗きに行く。そこには美しい娘と談笑する弟がいた。兄は、戸口の外に一枚の虎の皮が置かれているのを見つけ『隣近所にあのような娘はいない、あれはきっと虎の化け物だ』と勘づく。そうして兄は、虎の皮を自分の家に持ち帰って隠す。
次の朝、虎の皮がないことに気づいた娘は弟に食ってかかるが、弟は何のことかわからず、「何がないのか。はっきり言ってくれれば買って来てやるよ」と言う。しかし女は「買えないものなのよ」と地団駄を踏む。弟は実家に探しに行くよう提案し、ついでに兄夫婦に紹介する必要性を説く。
家に来た弟に対して、兄は自分が隠した皮のことを話す。二人は「皮を戻すと、元のすがたになって出ていくだろう」としてそのまま隠し続ける。女はそのまま弟と夫婦として暮らし、家の者から好かれ、一男二女をもうける。
子どもたちが大きくなると、兄夫婦が「お前たちの母親は虎の精だよ」ともらしてしまう。子どもたちは母親にそれを言うと、母はカッとなって跳び上がった。それから、女は毎日夫といがみ合うようになり「あたし出ていくわ。ここにはもう住めなくなった。あたしの着るものを早く返してよ」と言う。
弟は兄に相談する。「子どもも生まれたし、もうあいつに皮を返して出て行かそう」と言う話になり、兄は女の虎の皮を出して返してやる。すると女はすぐさまそれを身に着けて地面に一回転するなり、たちまち一頭のまだらの猛虎に変じた。そうして虎は兄の嫁とその二人の子どもを大口を開けて喰って、門から出て行った。
(「虎女房」、『中国の昔話』澤田瑞穂訳、1975年、109頁)
小澤俊夫「世界の民話」p.133-35からの要約。
Ⅲ動物が人間の女性の姿をしているとき、むりに妻にされる
- 天人女房(日本)
- 人間の妻になった鴨(イヌイット)など…
(参考…小澤俊夫「世界の民話」pp.142-157/1979年/中央公論社)
あるところに、母に「嫁を貰え」と勧められてもなかなかもらわない若者がいた。ある日、カヤックに乗って猟にでかけたさい、なかなか獲物がとれず川上を登っていき、河原に上陸してしばらく歩いていると、裸の娘たちがかくれんぼしているのを居つける。
そのうちの一番美しい娘に心を惹かれた若者は、ちょうどその娘がこちらに駆けて来たときにとびかかって捕まえ、そのまま女房にすると言う。
娘は嫌がるが、若者は聞かず、カヤックに連れてくる。腹が減ったといいう話になり、「あざらしの肉をやる」と言うが、娘は「そういう食べ物は知らないの」と言いい、手を触れることすらしなかった。その晩二人はカヤックで眠り、翌日家に帰る。
家に帰ると、息子が嫁を連れて来たことを母親は喜んだ。しかし、娘は肉を食べず、みなが寝静まってからひと山の草を摘んで食べた。やがて妻は息子と娘を産んだが、それでも草しか食べないので年老いた母親は「いつも草ばかり食べるなんて、おかしな子ね。あんたは鴨なの?」と言う。それを聞いた娘は大層怒り、泣きながら家に入って、二人の子どもに着物を着せると子どもたちを連れて出て行った。
帰宅した若者は、妻がいなくなったことを知り、老母を責める。そうして自分も家から出ていく。老母は泣いて止めようとするが、息子は翌朝妻の足跡をたどって捜しに行く。
途中小屋を見つけた若者は、焚き火のあとを見つける。一軒の家にいた男に斧を与えると、妻の行った道を教えてくれる。次の家ではあざらしのズボン、3番目の家では毛皮のマントを与えて道を教わる。3番目の家の男には「追うのをやめろ」と言われるが、教わった通りに大きな湖まで行く。しかし、カヤックも斧もなかったので湖を渡ることができず、疲労で死ぬよりほかにはないと思いながら眠り込んでしまう。
気が付くと、アカギツネに足を引っ張られて目が覚める。きつねはずきんをはねのけて人間の姿になり、若者に「どこから来たのか」尋ねる。わけを聞いたきつねは、「向こうに見える大きな山に登らなければならない」と教えてくる。途中にエスキモーの死体があるが、一瞬も立ち止まらずに頂上を目指さなくてはならないという。頂上には大きな集落があり、そのなかの一番大きな家に妻がいると言う。
若者は集落にたどり着く。一番大きな家から二人の男が出て来たので、木の枝で殴って殺して埋める。そうしているうちに家から子どもが出て来て、自分の父親がやってきたことを告げる。夫は家に入り、妻と再会する。
妻は「エスキモーがここへ来られるわけない」と言い、「ここはあたしの国、鴨の国よ」と言ってここにいるのが自分の夫であることを信じなかった。若者がここまできた経緯を話すと、妻はようやく信じる。
妻の老母は、若者に食べ物(木いちごと小さな魚2~3匹)を勧めるが、若者はこの食べ物に慣れていなかったので少ししか食べなかった。妻の父は「ここにはなんでもある」と言って、若者と鴨の妻は一族で共に暮らす。
そうしてある時、エスキモー鴨の大群が一族を襲って来たため、若者は杖で毎日襲来する敵を倒す。その内の数羽を持ち帰り、料理してもらうよう姑に頼むが、姑は「こういうものはわたしたちは食べないの」と言って一度は断る。頼み込むと料理してくれる。
そうして妻が2人目の息子を産むと、若者は息子と娘を残し、妻と赤ん坊を連れて去った。「たぶん、もう二度と戻ってこないでしょう。道は遠いですからね。」と言って。
小澤俊夫「世界の民話」p.152-155からの要約。
▽「蛇女房」にまつわるつぶやき